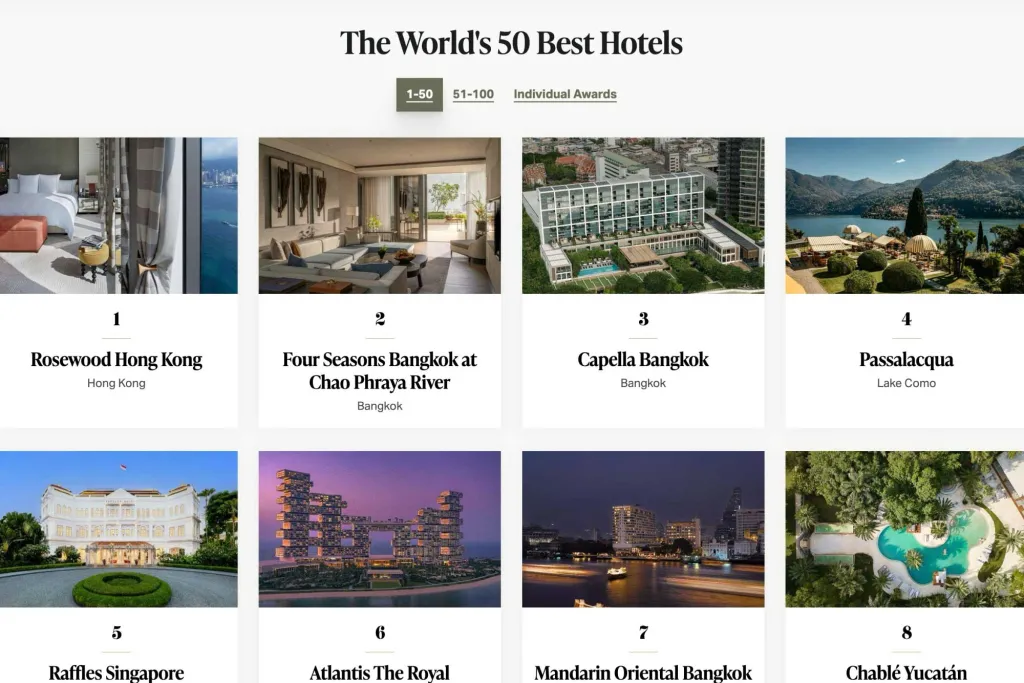目次
日本三名園の一つであり、国の特別名勝である「兼六園」。 加賀百万石の栄華を今に伝えるこの庭園が、2026年(令和8年)、かつてない大きな転換点を迎えようとしている。
2026年1月、石川県の馳浩知事は、現在「国有地」である兼六園を「県有地」へと転換する構想を正式に打ち出した。明治7年(1874年)の一般開放から約150年。長きにわたり国の管理下(実質的な管理は県への委託)にあった庭園を、県が所有権を持って運営するという構想。 実は、この巨大プロジェクトの裏には、長年兼六園を見守り続けてきた一人の人物の「提言」と、縦割り行政の弊害に苦しむ「現場の葛藤」があった。

第1章:発端は「現場の苛立ち」――宇田直人氏が鳴らした警鐘
1-1. 兼六園を自由に活用できないもどかしさ
「世界に誇る兼六園がありながら、我々は手足を縛られたまま何もできない」 今回の県有化構想、および大胆な再整備計画。そのすべての始まりは、行政主導ではなく、現場からの悲痛な叫びだった。
声を上げたのは、兼六園観光協会理事長であり、園内で最も古い歴史を持つ茶店の一つ「兼六亭」の代表取締役社長、宇田直人氏である。 宇田氏は長年、兼六園の現場に立ち続け、来園者の変化やニーズを肌で感じてきた。
しかし、そこで直面し続けたのは、国の所有地であるがゆえの「がんじがらめの規制」だった。新しいイベントをやりたい、古くなった設備を直したい、もっと現代の観光客に喜ばれるサービスを提供したい。そう願っても、「文化財保護」と「国有地の規則」という厚い壁が立ちはだかった。
「兼六園を自由な発想で活用できない現状を変えなければ、この庭園に未来はない」 宇田氏によるこの勇気ある問題提起こそが、県を動かし、馳知事の決断を促す「全ての始まり」となったのである。
1-2. 構造的欠陥:「売り上げを上げてはいけない」という矛盾
宇田氏らが指摘する最大の問題点は、兼六園のいびつな収支構造にある。現在、石川県は国(財務省)から無償で兼六園の土地を借り受けている。タダで借りている以上、そこから「利益」を生み出すことは許されない。これが現行ルールの鉄則である。
そのため、兼六園の予算編成は奇妙なバランスの上に成り立っている。「入園料収入(売り上げ)= 維持管理費(経費)」つまり、収支がプラスマイナスゼロになるように施策を行わなければならないのだ。もし黒字(利益)が出れば、それは「国からタダで借りた土地で県が儲けた」ことになり、問題視されてしまう。
この「黒字を出してはいけない」という縛りが、兼六園の首を絞めている。利益が出ない予算組みでは、最低限の剪定や清掃(現状維持)しかできない。余剰資金が生まれないため、新たな魅力創出への投資や、老朽化したインフラの大規模改修にお金を回すことが構造的に不可能なのだ。
「稼いでも投資に回せない」。
この悪循環を断ち切るには、県が土地を買い取り、自由に収益を上げて再投資できる仕組みに変えるしかない。それが宇田氏の、そして今回の県有化構想の核心である。
第2章:行政の「縦割り」が招く停滞――3つのバラバラな顔
2-1. 文化・土木・観光の不協和音
宇田氏の提言には、もう一つ重要な視点が含まれている。それは、兼六園を管理する行政組織の「縦割り」問題である。 現在、兼六園の管理運営は、以下の3つの異なる部署がそれぞれの論理で動いており、完全に独立してしまっている。
- 文化政策(文化財保護): 「文化財としての価値を守る」ことが最優先。現状変更を極端に嫌う。
- 土木(維持管理): 「公園施設としての物理的な維持」が仕事。道路や樹木の管理を行うが、観光的視点は希薄。
- 観光(誘客): 「多くの人に来てもらいたい」とPRを行うが、現場の規制緩和を行う権限はない。
これら3つの部署が足並みを揃えていないため、例えば「観光客のために新しい体験を作りたい(観光)」と思っても、「文化財だからダメだ(文化)」、「前例がない工事はできない(土木)」といった具合に、互いに牽制し合い、物事が前に進まない状況が続いていた。
2-2. 求められる「兼六園庁」のような統括機関
「3つのバラバラな組織では、兼六園という一つの人格を支えきれない」 宇田氏や観光協会が求めているのは、これらを統合し、強力なリーダーシップのもとで意思決定を行う統括機関(例えば「兼六園庁」や専門の公社のような組織)の設立である。 県有化は、単に土地の持ち主が変わるだけでなく、こうした行政の縦割りを解消し、経営視点を持った組織へと生まれ変わるための絶好の機会でもあるのだ。
第3章:2025年後半。改革の始まり――「維持管理」から「未来への投資」へ
3-1. 馳知事が打ち出した「県有化」の真意
「今のままでは、兼六園は『現状維持』しかできない。未来へつなぐためには、石川県がオーナーシップを持つ必要がある」 2026年1月、馳浩知事の発言は、多くの県民や観光関係者に驚きをもって受け止められた。
現在、兼六園の土地は財務省が所有する「国有地」である。石川県は国から無償で貸付を受け、維持管理を行っている立場だ。一般的に考えれば、国が所有しているほうが財政的にも安心であり、なぜわざわざ県が巨額の費用を投じて土地を買い取る必要があるのか、疑問に思う声も少なくない。
しかし、知事が指摘した問題の本質は、前章で述べた国の制度的な「足かせ」にあった。 現行の「地盤国有公園」という枠組みでは、国から認められる予算や行為は、原則として「維持管理」に限定されている。
つまり、崩れた石垣を直す、枯れた木を植え替えるといった「マイナスをゼロに戻す作業」は認められるが、新たな魅力を創出するための大規模な改修や、時代に合わせたインフラ整備といった「未来への投資(プラスの作業)」は、法的な制約により極めて困難となっている。
3-2. 年間250万人の重圧と「老い」
兼六園の来園者数は、年間約257万人(うち外国人約60万人)に達する。 これだけの数の人間が毎日地面を踏みしめることによる「踏圧(とうあつ)」の影響は深刻だ。
土壌はコンクリートのように硬化し、樹木の根は呼吸困難に陥り、名松の老朽化が進んでいる。 「維持管理」の範疇だけでは、これらに対する抜本的な土壌改良を行うことすら難しい。さらに、インバウンド需要の急増に伴い、多言語対応やバリアフリー化、高品位な文化体験の提供など、現代の観光地として求められる機能は高度化している。 国の所有である限り、予算獲得には財務省との折衝が必要であり、全国一律の基準が適用されるため、兼六園独自の事情に即した迅速な投資ができない。
「兼六園をディズニーランド化するつもりはないが、今のままでは文化財としての価値を毀損してしまう」
知事の言葉には、このままではジリ貧になるという強い危機感が滲んでいる。県有化は、兼六園を「守りながら攻める」体制へと移行するための不可欠な第一歩なのである。
第4章:再整備の全貌――「本物志向」と交通ハブ化
県が所有権を取得した後、具体的に兼六園はどう変わるのか。 発表された構想は、単なる庭園の手入れにとどまらず、金沢の都市構造そのものを変える可能性を秘めている。
4-1. 「本物志向」への原点回帰
再整備のキーワードとして掲げられたのは「本物志向」である。 これは、決してテーマパークのような派手なアトラクションを作るということではない。むしろ逆だ。
兼六園を作庭した加賀藩主(前田綱紀・斉広・斉泰)らの本来の理念に立ち返り、長い年月の中で損なわれてしまった景観や植生を、あるべき姿に戻す試みである。
そのモデルケースとなるのが、隣接する「金沢城公園」だ。 金沢城は、県有地として「復元文化財」という明確なコンセプトのもと、伝統工法を用いた菱櫓・五十間長屋などの復元整備が進められた。そこには宮大工や左官職人の技術が結集され、現代における「本物の歴史空間」が創出されている。
兼六園においても同様に、硬化した土壌の大規模な改良を行い、弱った植栽を更新する。さらに、能楽などの伝統芸能を本来の形式で披露できる空間を確保するなど、ハード・ソフト両面から文化財的価値を高める計画だ。「ただ古いものを残す」のではなく、「生きた文化遺産」として磨き上げる。それが県有化後のグランドデザインである。
4-2. 兼六駐車場の「バスターミナル化」構想
庭園本体の整備と並行して注目されているのが、周辺エリア、特に「兼六駐車場」の大改造計画だ。 現在の兼六駐車場は、観光バスと一般車両が混在し、シーズンには入庫待ち。車列が周辺の渋滞を引き起こしている。 県の新構想では、この駐車場の1階部分を大規模な「バスターミナル」へと作り変える。
これには、単なる駐車スペースの確保以上の、戦略的な狙いがある。
- ① 金沢駅「一極集中」の緩和
- 現在、石川県を訪れる観光客の多くは金沢駅(鼓門周辺)に集中する。駅からバスで兼六園へ向かうルートがパンク状態になることも珍しくない。兼六園に巨大なバスターミナルを整備することで、観光客を駅を経由させずに直接兼六園エリアへ誘導する新たな動線を作る狙いがある。
- ② 広域観光のハブ機能
- バスターミナル化の真の目的は、「通過点」から「拠点」への転換だ。 兼六園を観光した旅行者が、ここを起点として能登、加賀、さらには福井や富山へと向かう「二次交通」のハブ機能を担わせる。 特に、震災からの復興を目指す能登方面への特急バスの発着点とすることで、金沢に滞留しがちな観光客を県内全域へ分散(周遊)させる。これは「オーバーツーリズムの解消」と「地方への経済波及」を同時に解決する一手となり得る。
- ③ インクルーシブな機能強化
- バスターミナルには、手荷物預かり所、多言語観光案内所、そして高齢者や障害者にも優しいバリアフリー設備が完備される予定だ。到着してすぐに手ぶらで庭園散策を楽しめる環境は、旅行者の満足度を劇的に向上させるだろう
第5章:論争必至の「二重価格」と経済戦略
県有化構想の中で、最も県民や国民の関心を集めているのが「お金」の話である。 県が土地を買い取り、大規模な整備を行うには莫大な財源が必要となる。その原資をどう確保するのか。ここで浮上しているのが「二重価格制」の導入だ。
5-1. 観光客と住民の「価格分離」
現在、兼六園の入園料は大人320円(2026年時点)。これは世界的知名度を持つ文化遺産としては破格の安さと言える。 県は、県有化に伴う入園料の改定において、県民と県外観光客(特にインバウンド)で料金に差をつける「二重価格」の導入を検討している。 例えば、県民は据え置き、あるいは微増にとどめる一方で、観光客からは1,000円〜2,000円程度の料金を徴収する可能性がある。 近年、姫路城が外国人観光客向けの入園料を大幅に引き上げる検討を始めたように、日本の観光地では「安すぎる入場料」の見直しが進んでいる。
5-2. 収益の還元と「稼ぐ文化財」
「高い料金を取って儲けようとしている」という批判に対し、県は明確なビジョンを提示する必要がある。 増収分は、決して県の一般財源(他の公共事業など)に消えるわけではない。老朽化した茶店の耐震化、トイレの洋式化・多機能化、そして前述した土壌改良や植栽管理といった「庭園を守るための費用」に直接再投資される。 また、知事が「文化ゾーン全体の魅力向上」と述べているように、兼六園単体だけでなく、周辺の金沢城公園、21世紀美術館、本多の森公園などを含むエリア全体の回遊性を高めるための資金としても活用されるだろう。 「観光客から適正な対価を頂き、それを文化財の保全と質的向上に充てる」。この「稼ぐ文化財」への転換こそが、持続可能な観光地経営の鍵となる。
第6章:歴史は繰り返す――昭和51年、「有料化」という苦渋の決断
2026年の県有化構想が「未来への投資」であるならば、その土台となっているのは、50年前に断行された「有料化」という過去の闘いである。 「公園は市民のために無料であるべきだ」という理想と、「このままでは庭園が死んでしまう」という現実。その狭間で揺れ動いた歴史を知ることで、今回の県有化の重みがより鮮明になる。
6-1. 大正時代から燻っていた「有料化」
実は、兼六園を有料にすべきか否かという議論は、大正時代から存在した。 大正5年(1916年)、兼六園保勝会の依頼で調査を行った原凞(はらひろし)農学博士は、すでに当時から「名園としての風致を保存するためには、入園制限(有料制)もやむなし」という提言を行っていた。 しかし、当時は「公園開放の原則」が強く、市民の反発も予想されたため、「時期尚早」として見送られている。
6-2. 戦後の荒廃と「観光公害」の始まり
事態が急変したのは、戦後の高度経済成長期である。 昭和30年代後半から40年代にかけて、観光ブームとともに兼六園の入園者は爆発的に増加した。昭和39年には137万人、昭和47年にはついに200万人を突破する。 当時の兼六園は無料開放されていたため、昼夜を問わず人が押し寄せた。
その結果、何が起きたか。 園路の土は踏み固められ、苔は剥げ落ち、松や桜などの樹勢は著しく衰えた。曲水(用水)にはゴミが投げ捨てられ、水質汚濁も深刻化した。
さらに昭和36年の第二室戸台風による倒木被害も重なり、兼六園は「名園」の姿を失いつつあった。 「このままでは兼六園がダメになる」
昭和38年頃から、金沢商工会議所や観光協会といった経済団体からも、有料化を求める声が上がり始めた。かつて反対していた市民の間でも、昭和50年のアンケートでは「保護のためなら有料化もやむを得ない」という意見が多数を占めるようになる。
6-3. 102年目の決断
そして昭和51年(1976年)、当時の中西陽一知事がついに決断を下す。
明治7年の一般開放以来、102年間続いてきた「無料」の歴史に終止符を打ち、9月1日から有料化を実施したのである。
当時の料金は大人100円、小人50円。 この有料化には、明確な哲学があった。
「単なる観光収入のためではない。文化財としての『保存』を最優先し、入園者を適正に制限するための措置である」 そのため、得られた収入はすべて園の保護・維持管理に使われることが約束された。
また、県民感情への配慮も徹底された。 「早朝無料開放」は、毎朝散歩を楽しむ市民のために残された。年末年始や観桜期、百万石まつりの期間も無料とした。高齢者や障害者、地元の小中学生の遠足は免除された。 「県民の庭」としてのアイデンティティを残しつつ、文化財を守るための現実的な解としての「有料化」。それは、行政と市民が対話を重ねて出した、ギリギリの妥協点であり、英断であった。
第7章:1976年から2026年へ――「守る」から「高める」フェーズへ
7-1. 50年前の精神を受け継ぐ
1976年の有料化は、荒廃する庭園を物理的に「守る」ための防御策だった。 対して、2026年の県有化は、守られた庭園の価値をさらに「高める」ための積極策と言える。
しかし、両者に共通しているのは、「現状維持は後退である」という認識だ。
昭和の時代、何もしなければ兼六園は踏み荒らされて消滅していたかもしれない。 令和の今、何もしなければ兼六園は「ただの古い公園」として世界から取り残され、陳腐化してしまうかもしれない。
中西知事が「無料のタブー」を破ったように、馳知事は「国有のタブー」を破ろうとしている。 その根底にあるのは、郷土の宝を次の100年に継承したいという、変わらぬ情熱である。
7-2. 課題と今後の展望
もちろん、県有化には多くのハードルがある。 数百億円とも言われる土地購入費の財源確保、財務省との法的な調整、そして二重価格に対する県民や観光客の合意形成。 「県民は安くて、観光客は高いのか」という不公平感をどう払拭するか。
「バスターミナルができれば、周辺の静寂が損なわれるのではないか」という懸念にどう答えるか。 石川県は今後、文化、観光、庭園の専門家や経済界、産官学の代表で構成する協議体を設置し、議論を深めるとしている。 トップダウンだけでなく、50年前のように県民を巻き込んだ丁寧な議論が必要不可欠だ。
さいごに
兼六園の県有化構想は、一地方自治体の施策という枠を超え、日本の文化財行政全体に一石を投じるモデルケースとなる可能性を秘めている。 国任せにするのではなく、地元が責任を持って所有し、管理し、投資する。
観光客数という「量」を追うのではなく、体験の「質」を高めて対価を得る。 そして、その収益を再び文化財へ還流させる。 この循環を作り出せるかどうかが、人口減少社会における日本の観光立国の成否を握っていると言っても過言ではない。
六つの勝景(六勝)を兼ね備えた名園は、令和の時代に「保存」と「活用」、「伝統」と「革新」をも兼ね備えた、新たな姿へと進化しようとしている。 金沢市民の誇りであり、日本の至宝である兼六園。 その未来を決める議論は、まだ始まったばかり。
兼六園有料化までの歴史と経緯
| 時代 | 年月 | 出来事・内容 | 背景・詳細 |
|---|---|---|---|
| 明治期 | 明治7年(1874) | 一般開放開始 (無料) | 太政官布告に基づき公園として開放。県に財源がなく、園内での茶店営業を許可し、管理の一部を負担させる形式をとった。 |
| 明治中期 | 荒廃と風紀の乱れ | 自由な利用により、樹木が傷んだり、風紀を乱す茶店が出るなど、保存上の問題が浮上し始める。 | |
| 大正期 | 大正5年(1916) | 【最初の有料化提案】原凞(はらひろし)博士の提言 | 兼六園保勝会が招いた原博士が「名園として保存するなら入園制限(有料制)もやむなし」と提言。しかし「公園は開放すべきもの」という反対論が強く、時期尚早として見送られた。 |
| 大正11年(1922) | 「名勝」指定 | 国により名勝に指定される。保存の機運は高まるが、無料のまま維持される。 | |
| 昭和期(戦前) | 昭和2〜10年頃 | 市への移管論 | 県の財政難から「金沢市へ移管してはどうか」という議論が県議会で出たが、県が管理を継続することになった。 |
| 昭和期(戦後) | 昭和20年代 | 戦後の混乱と荒廃 | 戦時中の松脂採取や食糧増産のための開墾、戦後の資材不足などで園内は荒廃していた。 |
| 昭和31年(1956) | 【有料化の再提案と却下】田谷知事の反対 | 県土木部が荒廃防止のため有料化を立案。しかし田谷充実知事が「市民の憩いの場を取り上げるのは忍びない」として反対し、有料化は見送られた。代わりに「管理条例」を制定。 | |
| 昭和30年代後半 | 観光ブームと限界 | 観光客が急増(昭和37年に130万人突破)。踏圧による老樹の衰弱、苔の消失、用水の汚濁など「観光公害」が深刻化。保存と利用のバランスが崩壊し始める。 | |
| 昭和38年(1963) | 「保存懇話会」発足 | 県が「兼六園保存懇話会」を設置。以後、観光協会や商工会議所などから有料化による抜本的な保護対策を求める声が高まる。 | |
| 昭和42年(1967) | 県議会での議論 | 奥田敬和県議らが「老樹対策は待ったなし」として早期有料化を強く主張。中西知事は「無料開放は全国に誇るべきもの」としつつも、保存の必要性を痛感し始める。 | |
| 有料化決定 | 昭和50年(1975) | 【世論の変化と決断】 | 入園者が280万人を超え、保存の限界に達する。県民アンケートで「有料化やむなし(賛成)」が約8割を占めたことを受け、中西知事が有料化の方針を議会で表明。 |
| 昭和51年(1976) | 実施計画の策定 | 「有料化懇話会」などで詳細を検討。「得られた収入はすべて園の保存・整備に使う」「早朝や特定の日は無料にする」などの配慮を決定。 | |
| 実施 | 昭和51年(1976)9月1日 | 【有料化スタート】 | 102年間の無料の歴史に幕。・料金:大人100円、小人50円・目的:文化財庭園としての保存・維持管理・無料措置:早朝開放、高齢者(65歳以上)、年末年始・観桜期などの特定日。 |
| その後 | 昭和60年(1985) | 「特別名勝」指定 | 有料化による財源で管理・保護事業が手厚く行われたことが評価され、国の「特別名勝」に昇格した。 |
解説:有料化のポイント
• 「公園」から「庭園」へ: 明治以降、兼六園は「みんなの公園」として運動会や集会に使われてきましたが、有料化はそれを「鑑賞するための文化財庭園」へと定義し直す大きな転換点でした。
• 県民への配慮: 「市民の憩いの場」としての機能を残すため、早朝の無料開放(ラジオ体操や散歩用)や、観桜期・お盆などの無料開放日が設けられました。これは有料化反対派への妥協点でもありました。
• 収入の使途: 入園料収入は、松の雪吊りや剪定、苔の保護、曲水の護岸修理など、莫大な費用がかかる維持管理費に充てられています。